人間関係の中で、自分とは違う考えを、まるでそれが正しいかのように主張する人に出会ったとき、あなたはどうしていますか?
多くの場合、議論の余地があるかどうかを見極めながら、3割ほど話して、7割は聞き流す。そんな対応をしているかもしれません。それも一つの大切な対処法ですが、関係性としては平行線のままになってしまうこともあります。
私が他者との関係づくりで意識しているのは、「相手の味方であること」です。
これは、敵か味方かで分けるという意味ではありません。意見が違う相手に対して、「この人は何を伝えようとしているのか」「何を大切にしているのか」と考える余白を持つために、私が出会った言葉です。
一呼吸おいて、「この人も同じ方向を目指す味方かもしれない」と意識できると、まずは話を聞いてみようと思えるのではないでしょうか。その先に、対話が生まれる可能性も広がります。
私は教育現場で、子どもへの見方や考え方が異なる人たちと多く出会ってきました。でも、「この人も子どものことを一緒に考える味方だ」と思えたとき、不満は減り、同じ方向を見ながら話ができるようになりました。
この「味方」という言葉と出会ってから、話すことが楽しくなったのを覚えています。相手の考えをもっと知りたい、聞いてみたいと思えるようになったのです。
「味方」という言葉は、自分自身の立ち位置を表す言葉でもあります。相手が“子ども”や“障害児者”“高齢者”など、相手が誰であっても自分が他者とどんな関係を築きたいのかを考える中で、対峙するのではなく、同じ方向を見ながら人生を共に考えたい。そんな関係づくりの軸ができたことは、私にとってとても大切な変化でした。
信頼関係を築くために必要なのは、相手が安心して話せる状態をつくること。最初は簡単ではないかもしれません。でも、まずはその人が見ている側に立って、同じ位置から世界を見てみようとすることから始めてみませんか。
そうすれば、きっと相手も心を開いてくれるはずです。
「わたしはいつでもあなたの味方です。」
「あなたは、誰かの味方になれていると感じる瞬間はありますか?」
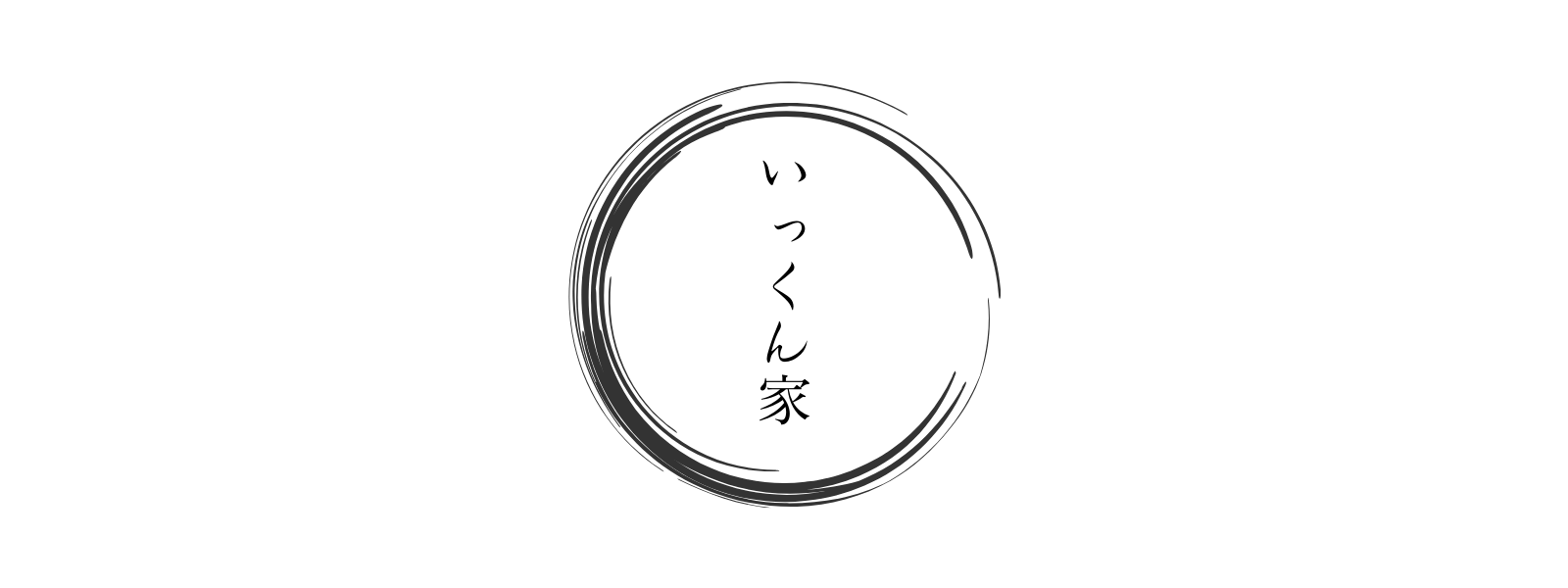



コメント